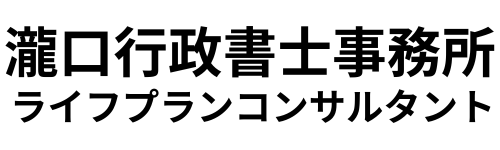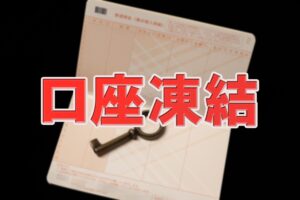生前対策情報
この土地は亡くなった祖父の名義になっています。最近「相続登記の義務化」というのを聞いたのですが、どういうものかよくわからない。「心配だなぁ~」というそんな方の疑問にお応えします。 「相続登記の義務化」を簡単解説します。
<背景> 所有者不明土地問題の解決毎年4~5月頃に、市区町村から不動産にかかる税金、固定資産税の納付書が届きます。 その納付書の名義が先代のまま届いているということがあります。相続時に登記しないと、現在の持ち主が誰なのか […]
不動産(土地・建物)にはいろいろな評価方式があってわかりずらい。今回は「相続税評価」と「実際の財産価値」について解説していきます。
固定資産税評価額、路線価方式、倍率方式その他いくつかの評価方式がありますが、財産の種類ごとに、相続税評価の方法を対比しながら説明していきます。概要は下表の記載とおりです。是非参考にしてください。 財産の種類 相続税評価の […]
認知症の進行と預金口座利用対策
認知症 の人については 預金口座が凍結されます。この凍結予防対策として 、成年後見人制度と 家族信託制度と 銀行の代理人指定システム等があります。それぞれの制度 について、 認知障害の進行度合いとの関係で 利用手続きを […]
「見守りサービス」のご紹介 (警備会社機動隊員の駆け付けサービス+緊急通報サービス:警察・消防署・ご家族等へ)で安心安全を!! 対象エリア:①足利・桐生待機所 ②邑楽・館林待機所 ③太田・大泉待機所 ④前橋・赤堀待機所 ⑤伊勢崎待機所 ⑥高崎藤岡待機所 ⑦前橋待機所 ⑧富岡待機所から25分以内で駆け付けることができるエリアです。
機械警備・ホームセキュリティ :おひとり様・高齢者お二人世帯向け今回の紹介内容のポイント次のとおりとなります。1)警備保障会社とお客様との直接契約です 2)月額警備料金は次の通り①「見守り」プラン ②「見守り+火災セン […]
うちは大丈夫かな?気になる相続税のポイントを解説します。
相続といえば、最初に頭に浮かぶのが相続税のことではないでしょうか? 気にはなるが、何か難しそうなので確認が後回しになりがちなテーマです。 知っておいて欲しい内容を絞って解説します。是非参考にしてください。詳しい内容・試算 […]
相続税の負担軽減策「土地の評価額を最大8割減額可能な小規模宅地等の特例」をポイント説明
自宅や事業に利用していた土地を特定の人が引き継いだ場合に、土地の評価額を最大8割減額できる「小規模宅地等の特例(国税庁HP)」について取り上げます。その内容、利用するための条件を確認しておきましょう。土地の評価額が2割に […]
想いを実現し、笑顔・感謝が生まれる賢い贈与の仕方を解説します!!生前贈与シリーズ:基礎編(6)
2つの異なる年間110万円の非課税枠(国税庁作成リーフレット「1ページ」参照)を解説します。2024年1月から改正施行された相続時精算課税制度においても、110万円の非課税枠が利用できるようになりましたが、暦年課税での非 […]
想いを実現し、笑顔・感謝が生まれる賢い贈与の仕方を解説します!!生前贈与シリーズ:基礎編(5)
今回は、どんな場合に生前贈与をしたら良いのか?、どんなステップを踏んで進めていったらよいか?を考えていきます。まずは、財産の整理、評価など現状把握と分析を行ない相続税がかかるかシミュレーションします。節税目的であれば相続 […]
想いを実現し、笑顔・感謝が生まれる賢い贈与の仕方を解説します!!生前贈与シリーズ:基礎編(4)
前回「基礎編(3)」での、贈与税が非課税になるパターンの「①贈与税の非課税枠(暦年課税110万円)、②相続時精算課税(最大2500万円。2024年からは暦年課税110万円も使える)」に引き続き、今回は「③贈与税がそもそも […]
想いを実現し、笑顔・感謝が生まれる賢い贈与の仕方を解説します!!生前贈与シリーズ:基礎編(3)
前回「基礎編(2)」、贈与税に関する「控除(配偶者控除と基礎控除)」「申告が必要なケース、申告期限、納付」「計算方法(暦年課税)」等をご紹介しました。今回「基礎編(3)」は「計算方法の続編として(相続時精算課税制度)」か […]
想いを実現し、笑顔・感謝が生まれる賢い贈与の仕方を解説します!!生前贈与シリーズ:基礎編(2)
今回の内容は、次の通りです。 <控 除> 配偶者控除と基礎控除 <申告が必要なケース、申告期限、納付> <計算方法> 暦年課税<注意点>・定期贈与・名義預金 <控 除> 1.配偶者控除⇒ 次の一定の条件のもとに、配 […]
想いを実現し、笑顔・感謝が生まれる賢い贈与の仕方を解説します!!生前贈与シリーズ:基礎編(1)
贈与の基礎 個別具体的な税務相談・税務申告などの実務については、税理士などの専門士業にお任せするとして、これまで努力を重ね資産形成された多くの方々にとって、生前対策をしっかりしておくことによって資産や事業を次の世代へ承継 […]
墓じまいは、どうしたら良いの? 誰に相談すれば。。。【太田市・足利市・桐生市・伊勢崎市・邑楽郡の方へ】
群馬県太田市、大泉町近郊で、今後子どもたちがお墓を管理していくのが難しい、負担をかけたくないなどの理由から、墓じまいをするには、誰に相談し、どのような視点から考えたらよいのか、その費用はどのくらいなのか、基本的な流れを解 […]
自分らしい終活:終末期の対策そして死後におこなう対策(死後委任事務)は?
前回おひとり様において、元気な老後期から体調が不調・不安な老後期にかけての対策をご紹介してきましたが、今回は終末期以降についておこないたい対策を考えていきます。 終末期終末期では、信託契約を活用して、財産管理や葬儀、相続 […]
おひとり様の生前対策はどうしたら良いの? 自分らしい終活
まず最初に、前回の繰り返しになりますが、生前に適切な対策を打たない限り、身寄りがなく相続人がいない場合、1)死亡直後の対処において、様々な物理的作業(遺体引取り、安置、葬儀・埋葬)と事務処理(死亡届、病院・施設費用の清算 […]
遺産が国のものになってしまうというのは、ホント?
今回からおひとり様の相続について考えていきます。まず最初に、多くの人に知っていただきたいことは、生前に適切な対策を打たない限り、身寄りがなく相続人がいない場合、次の2点です。1)死亡直後の対処において、様々な物理的作業( […]
生前対策が進まない理由を考える
生前対策の必要性を漠然と感じていても、まだ先のことだし、身近で対策が行なわれてない限り実感が乏しいのが一般的です。その根拠のない楽観論のため、何も具体的な対策を取らず、遺産を巡る争いや意思能力の低下によるトラブルに巻き込 […]
エンディングノートは家族の宝物・道しるべ
ご本人にしか知らない「財産状況、介護・入院・終末期医療の在り方、遺産分割の考え方、家族への感謝の気持ち、メッセージなど」を纏めたエンディングノートの重要性は人生の総決算と将来の希望を纏めたものとして広く知られています。 […]
こんなとき、どこに相談? 認知症相談窓口を紹介
最初に、「認知症について相談したい時や、介護予防サービスや介護保険サービスを利用したい時には、 各市町村に設置(中学校区内に1カ所)されている最も身近な地域包括支援センターが総合相談窓口になっています。 地域包括支援セン […]
こんな使い方ができる家族信託!! お悩み解決の活用例
家族信託は、高齢化社会や相続対策において有効な手段として注目されています。今回も、前回に続き、家族信託の代表例(視点を変えて)をいくつか紹介します。貴方のお悩み解決に近い例はどれでしょうか? 1.高齢の親の財産管理 親が […]
こんな使い方ができる家族信託!! 貴方のお悩み解決はどれ?
今回のテーマの家族信託では、「こんな上手な活用の仕方があった!!」 を紹介します。貴方のお悩みの解決方法はどの例が当てはまりますか? 詳しくは当事務所へお問合せください。 1. 自益信託での活用 信託の目的:委託者自身が […]
わからない!! 節税のための生前対策「贈与」をわかりやすく解説(入門編:後半)
前回(前半)で、贈与の基本的なことを中心に説明してきました。今回(後半)は贈与の種類・非課税枠、注意点、節税効果について取り上げます。 2. 贈与の種類と非課税枠 1)暦年贈与:毎年決まった金額を贈与する最も一般的な方法 […]
わからない!! 節税のための生前対策「贈与」をわかりやすく解説(入門編:前半)
贈与は、財産を他者に無償で譲渡する行為で、相続に備えた生前対策や、財産分散の手段として広く活用されます。 節税に活用できる贈与の基本的なこと、種類・非課税枠、注意点、節税効果について前半後半の2回に分けてわかりやすく説明 […]
遺留分減殺額請求権をわかり易く説明します
今回の紹介するテーマは、相続人の最低限の権利を守るための重要な制度である遺留分減殺請求権です。遺言の内容や財産の分配に不満がある場合や遺言を作成する場合に備え、知っておくことが大切です。 1.目的 相続人が最低限保障され […]